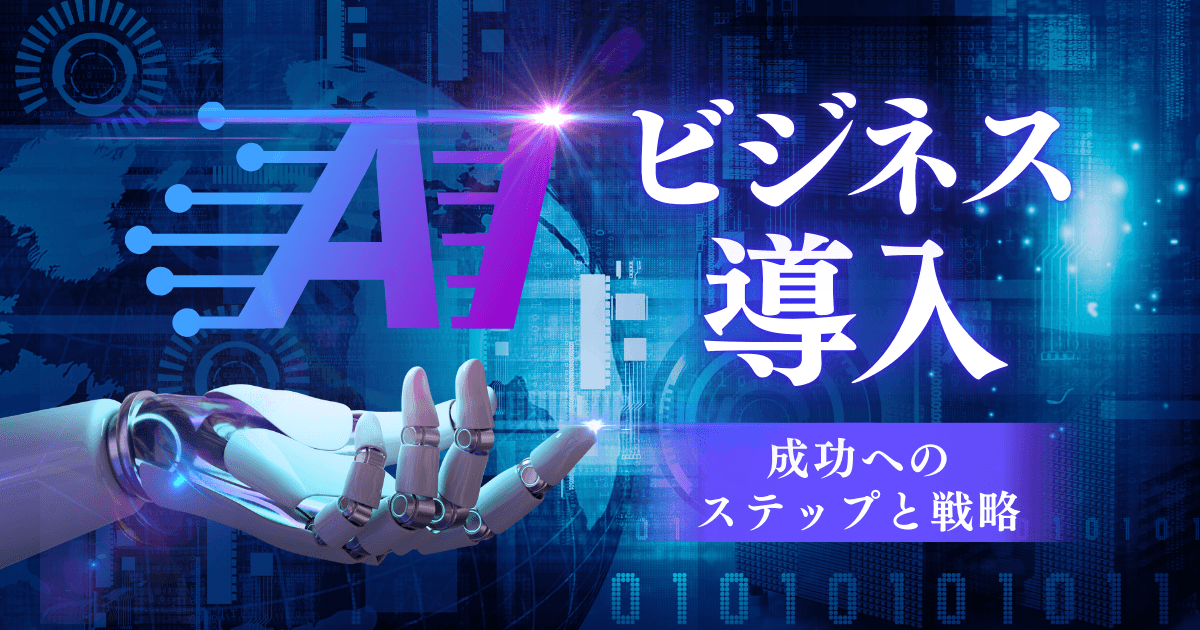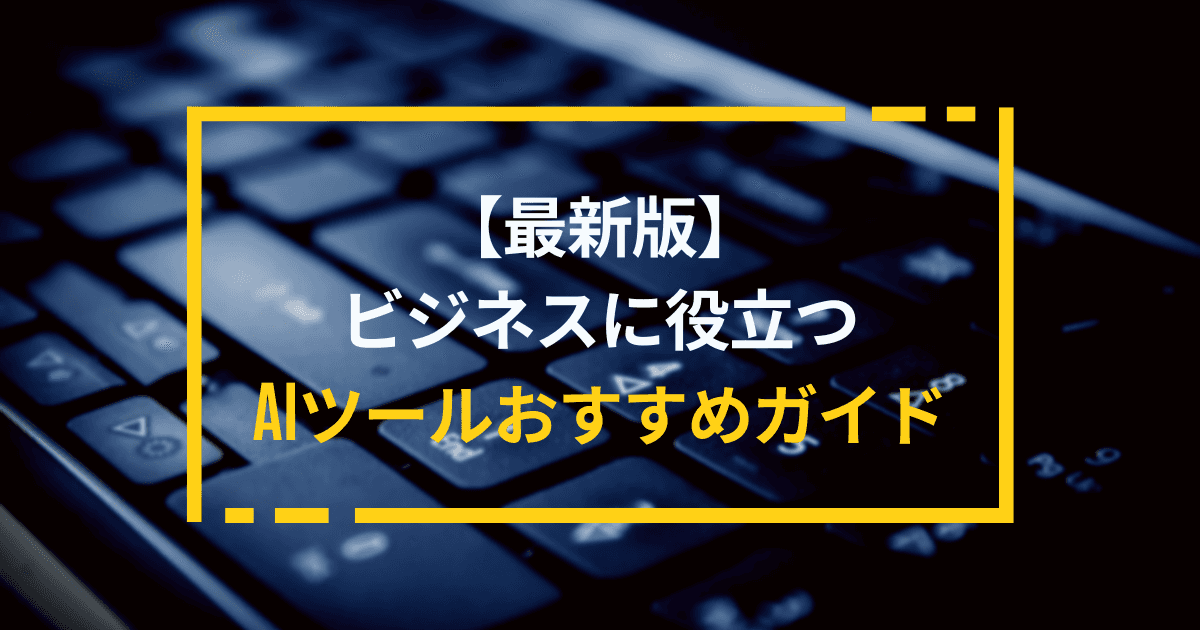こんにちは。
この記事では、大手企業のDeNAが約6000人いた社員数を約3000人に削減しながらも業務を滞りなく回そうとしている背景、そしてそのカギとして注目されている生成AIの活用について深掘りしていきます。
「でも、それって大企業の話でしょ?」と思われるかもしれませんが、実は中小企業こそ生成AIをうまく活かす大チャンスなんです。人手不足や予算の限られた状況でも、AI技術を上手に取り入れれば大きな効果が期待できます。
実際、私自身も仕事でAIを活用し始めてから、リサーチや文章作成の初稿づくりなどにかかる時間が減り、かなり業務効率が上がりました。「あれ?これだけでいいの?」と思うくらいシンプルに導入できるツールもあるので、まずは体験してみるのがおすすめです。
この記事では、以下のポイントについてお話しします。
1. DeNAがAIを活用する背景と動き
2. なぜ中小企業ほど生成AIを活用すべきなのか
3. 具体的な活用例(カスタマーサポート、ドキュメント作成、マーケティングなど)
4. 生成AI導入時の注意点と成功ポイント
なるべく専門用語はかみ砕いて説明するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
1. DeNAがAIを活用して業務効率化を進める背景
最近のニュースや経営発表で話題になったのが、DeNAが人員を約6000人から3000人にまで削減する一方で、既存の事業を問題なく継続しようとしているという話。実際には「リストラ」というよりも、「AIをフル活用して効率化を進める」「浮いた人材を新規事業に振り向ける」という経営戦略がベースにあるようです。
たとえば、
経理業務:AIで請求書の読み取りや仕訳作業を自動化
マーケティング:データを自動収集・分析してレポートをAIが生成
カスタマーサポート:チャットボットを導入して問い合わせ対応を自動化
といった取り組みが進められています。これはDeNAだけの動きではなく、IT業界全体で共通の潮流になりつつあります。
面白いのは、こうした「AIで生産性を高める」取り組みは社員研修から始まっているところ。全員にAIの基礎を理解してもらい、社内システムと連携できるよう整備をし、徐々に実務に落とし込んでいるわけですね。これらが軌道に乗れば、人員を半減させても十分に事業が回るという算段なんです。
2. なぜ中小企業も生成AIを活用すべきか?
「でも自社は大企業じゃないし…。AIなんて導入する予算もないし…。」と思ってしまう気持ち、すごくわかります。でも、実は中小企業ほどAIの恩恵を受けやすいんです。特に下記のような理由が挙げられます。
人手不足を補える
中小企業ほど人材確保が難しく、一人あたりの業務量が多いケースが多いですよね。生成AIを使ってルーティンワークを自動化できれば、限られた人材でより多くの仕事を回せるようになります。
コスト削減が可能
昼夜を問わず必要になるカスタマーサポートやコツコツしたデータ入力作業など、人件費が大きい部分をAIに置き換えることで、経営の負担を抑えることができます。実際、夜間のお問い合わせ対応をAIチャットボットに任せて、時間外手当を大幅に削減した企業もあるそうです。
AI導入コストが下がっている
「AI」と聞くと高度なITシステムや莫大な投資を想像するかもしれませんが、今はChatGPTのような大規模言語モデルを無料(あるいは低額)で使える時代になりました。専門知識がなくても使い始められるクラウド型のAIサービスも増えていて、初期投資を抑えての導入が可能になっています。
3. 中小企業がすぐに試せる生成AI活用の具体例
ここからは、「実際にどんな業務で生成AIが使えるのか?」という具体的な例を紹介します。ぜひ、身近な業務と照らし合わせてみてください。
(1) カスタマーサポートの自動化
AIチャットボットを導入し、よくある質問(FAQ)への回答を24時間対応化
お問い合わせ内容の振り分けを自動化し、複雑な案件だけ人間が担当
対応履歴を学習していくことで、回答精度がどんどん向上
メリット:顧客対応時間が減るうえに、深夜でも問い合わせ対応が可能に。担当者はより重要度の高い顧客対応やクレーム対応に集中できます。
(2) ドキュメント作成・管理をAIで効率化
会議の音声データから議事録を自動生成(文字起こし+要約)
提案書や契約書のひな型にAIが文章を埋め込む
定型文やマニュアルのドラフトをサクッと作成
メリット:デスクワークの時間を短縮し、人間はチェックや微調整に集中することで、書類のクオリティを保ちつつスピードを上げられる。
(3) マーケティングやSNS運用の最適化
AIがSNSの投稿文やブログ記事の下書きを量産 → A/Bテストで効果測定
広告文やキャッチコピーのバリエーションを一気に生成
過去データから、顧客に刺さりやすいキーワードや表現を提案
メリット:担当者の「アイデア出し」にかかる時間が減り、広告効果をより短期間で最適化できる。SNS担当が複数の仕事を兼務しているような場合でも、効率的に運用可能。
(4) データ分析と経営意思決定のサポート
過去の販売データをAIが学習し、次月以降の需要を予測 → 適正な発注量を決定
AIが顧客データを分析し、離反リスクの高い顧客を抽出 → 早めのフォロー
分析レポートをAIが自動生成 → 経営陣がすぐに把握できる
メリット:分析に時間とリソースを割かなくても、AIが一定レベルの予測や統計を出してくれる。意思決定のスピードが上がり、機会損失を防ぎやすくなる。
4. 生成AI導入時の注意点と成功のポイント
便利な生成AIですが、導入してから「使い方がわからない」「結局誰も使わない」なんてことにならないよう、以下のポイントに気をつけましょう。
AIツールの選定(無料 vs 有料)
無料のChatGPTやBingチャットなどから始めてみる
業務で使うなら、企業向けの有料版やサブスク型サービスを検討(サポートや契約面で安心)
目的を明確化
「問い合わせ対応を半自動化したい」「書類作成の時間を半分に減らしたい」など、ゴールをはっきりさせておく
効果測定や社内調整がスムーズになる
AIの出力精度や誤情報のチェック
生成AIはときどき、正しい情報のように見える誤情報を生み出す
必ず人間が最終チェックし、誤情報の拡散を防ぐ仕組みを作る
データ取り扱い・セキュリティへの配慮
社外クラウドAIに機密情報をそのまま入力しない
個人情報を扱う場合は、利用規約の確認や契約面の対策も忘れずに
小さく試し、徐々に拡大する
いきなり全社導入せず、一部の部署や業務だけでテストする
成功事例を社内に共有し、段階的に範囲を広げる
おわりに
DeNAのような大企業だけでなく、人手不足・リソース不足に悩む中小企業こそ、生成AIを味方につけて生産性を高める絶好の機会があります。特に最近は無料で使える高性能AIツールも増えているので、導入のハードルは想像以上に低いはず。最初から完璧に使いこなす必要はありません。「ちょっと試してみようかな」という気軽な感覚で始めても、意外なほどスムーズに成果が出たりします。
もし「実際にどう導入すればいいんだろう?」「もっと詳しい活用事例が知りたい」という方がいれば、ぜひコメントやフォローでご質問いただけると嬉しいです。私もAIを活用した業務改善や情報収集に強い興味があり、今後は私自身が試した具体的なノウハウも共有していく予定です。少しでも興味があれば、この機会に生成AIを取り入れてみませんか?